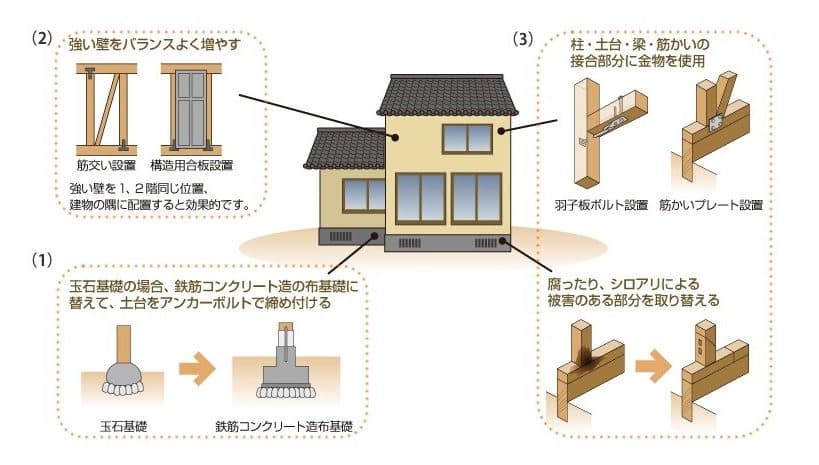★耐震補強工事を依頼すべきタイミングとは?
方法や費用相場もご紹介

地震大国である日本では、いつどこで大きな地震が発生するかわかりません。耐震補強工事を行って住宅の安全性を高めることは、大切な資産を守ることだけでなく、家族の安全を守ることにもつながります。
この記事では、耐震補強工事を依頼すべきタイミングを見極める5つの方法と、具体的な耐震補強工事の方法を解説します。耐震補強工事にかかる費用や工期、活用できる可能性のある補助金・助成金などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
★耐震補強工事を依頼すべき5つのタイミング
1.目安として建てたのが2000年以前である
築年数が40年以上経過している住宅は、1981年までに着工された「旧耐震基準」で造られた住宅の可能性が高いです。旧耐震基準は、震度5相当の地震を想定した耐震基準であり、震度6~7相当の地震に耐えられません。築40年以上の住宅にお住まいの場合は、耐震診断を受けて住宅の状態を確認することをおすすめします。木造住宅において法律の改正が2度ありました。まず1981年。その後1995年の阪神・淡路大震災を経て2000年に改正されました。2000年以前に建てられた住宅は耐震診断をおすすめします。
2.過去に増築や改築を経験している
過去に増築・改築を行っている場合は、接合部分の強度が不十分な可能性があり、地震による被害を受ける可能性があります。増改築を2回以上行っている住宅の場合は、より注意しなければなりません。
3.外壁のひび割れなど劣化が目立っている
外壁や基礎部分にひび割れが見られる場合や、住宅が傾いている場合など、建物の劣化が目立つ場合も要注意です。築年数が浅かったとしても、このような劣化が見られる場合は工事に問題がある可能性もあるため、耐震診断を受けましょう。
4.吹き抜けがある
吹き抜けがある住宅は、一般的な住宅と比較して柱と壁の量が少なく、地震が発生した際に建物全体がゆがむ可能性が高いです。目安として、1辺あたり4m以上の吹き抜けを設けている場合は、耐震診断を受けて状態を確認してください。
5.耐震診断の結果で総合評点の値が1.0を下回っている
耐震診断では、結果がIw値によって公開されます。これは、震度6強の地震に対する耐震性能を示す数値であり、以下4つのうちいずれかの評価を受けます。
【総合評点の値による評価の基準】
| 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
| 0.7~1.0 | 倒壊する可能性がある |
| 1.0~1.5 | 一応倒壊しない |
| 1.5以上 | 倒壊しない |
総合評点の値が1.0を超える場合は「一応倒壊しない」��「倒壊しない」に該当するため、安全です。
しかし総合評点の値が1.0未満の場合はリスクが高いため、耐震診断後のタイミングで耐震補強工事を依頼してください。